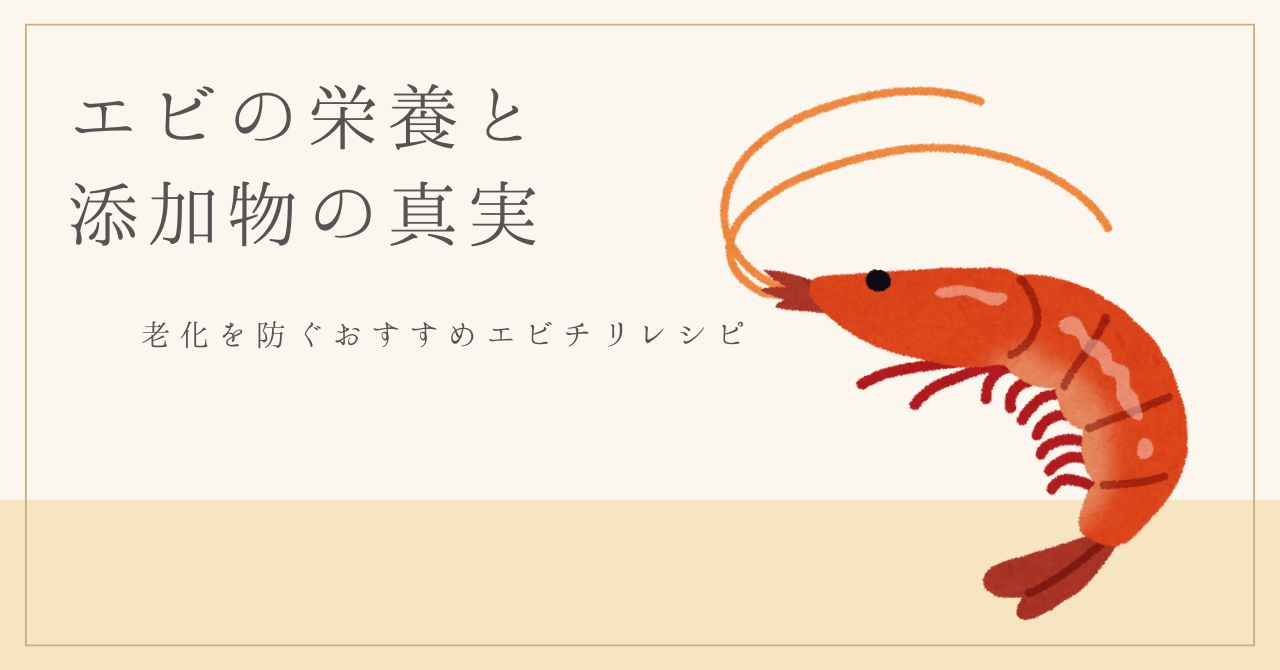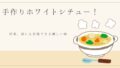「最近、疲れやすい」「なんとなく代謝が落ちてきた」そんな変化を感じることはありませんか?
50代になると、筋力の低下や代謝の変化を実感することが増えてきます。でも、食事を工夫することで、そんな悩みにアプローチできるとしたら? そのカギを握るのが 「エビ」 です。

50代の皆様こんにちわ。食生活アドバイザーのおーです。
エビは、低脂肪で高たんぱく、さらに ビタミンCやビタミンEをしのぐ強力な抗酸化物質「アスタキサンチン」 を含み、体の細胞を守る働きをしてくれます。つまり「美味しく食べながら健康管理ができる」理想的な食材です。
そうは言っても、新鮮なエビは価格が気になることもありますよね。そのため、手頃な価格で手に入る冷凍エビを活用する方も多いですが、これらには品質保持のために 添加物が使われることがあります。
一般的に使われており、すぐに健康に悪影響を及ぼすわけではありませんが、食品添加物の中には、長期間の摂取や食べ合わせの影響について、まだ研究が進行中のものもあります。そのため、できるだけ自然な状態のエビを選びたいと考える方が増えているのも事実です。
そこで本記事では、エビ本来の栄養メリットを最大限に活かすための「無添加エビの選び方」や、安心して楽しめる調理法、さらに美味しいエビチリのレシピまでを徹底解説!

この記事は、エビの栄養や無添加の冷凍エビの選び方を解説しつつ、健康的なエビチリのレシピを紹介しています。
「レシピだけ知りたい!」という方は、目次から最終章へジャンプしてください。
エビを上手に活用して、健やかで活力あふれる毎日 を目指しましょう!
エビのメリット提案
注目の栄養素「アスタキサンチン」
アスタキサンチンは、エビや鮭、カニ、ロブスターなどに含まれる 天然の赤い色素 です。
この成分は ビタミンCやビタミンEを超える強力な抗酸化作用 を持ち、健康や美容に役立つことで知られています。
老化の原因、活性酸素をコントロール!
強力な抗酸化作用で、フリーラジカル対策
私たちの体では、「活性酸素(フリーラジカル)」 という物質が自然に発生します。
活性酸素は 適量なら免疫力を高めたり、新陳代謝を促したりする など、大切な働きを持っています。
しかし、紫外線・タバコ・アルコール・ストレス・加工食品などの影響で 活性酸素が増えすぎると、健康な細胞まで攻撃してしまい、老化や生活習慣病の原因 になってしまいます。
アスタキサンチンのパワーでフリーラジカル対策!
そこで活躍するのが アスタキサンチンの強力な抗酸化作用!
✅ ビタミンCやEよりも優れた抗酸化力 で、活性酸素の暴走を防ぐ!
✅ 眼精疲労や視力低下の抑制にも効果的!
✅ 細胞の酸化ダメージを抑え、老化予防&免疫力アップをサポート!
✅ シワ・シミ・くすみなどの肌トラブル対策にも期待できる!
アスタキサンチンを豊富に含む エビやシャケを食べることで、自然と抗酸化パワーを補給 できます。
毎日の食事に取り入れることで、活性酸素のバランスを整え、アンチエイジング効果が期待できます!
自然由来の安心感
主な供給源
アスタキサンチンは、海藻やプランクトン(特に Haematococcus pluvialis という藻類)によって生成されます。エビやカニは、これらを食べることで体内に取り込み、赤くなるといわれています。
体内での作用
アスタキサンチンは脂溶性の成分であり、油と一緒に摂取すると吸収率が向上します。そのため、エビを使った料理では、オリーブオイルやごま油などの良質な脂質と組み合わせることで、より効果的に栄養を取り入れることができます。例えば、エビチリなら豆板醤やごま油を活用すると、風味と栄養の両方を引き出せます。
ラストで紹介するレシピでは、「塩分を抑えつつ、旨味とパンチを効かせたエビチリ」 を作れるコツもお伝えします!
エビから摂取できる栄養素
高タンパク
エビは、良質なたんぱく質が豊富に含まれており、筋肉の維持や修復に非常に適しています。肉類もタンパク質源ですが、赤身肉などはタンパク質は豊富なものの、カロリーが気になる場合もあります。
50代以降は筋肉量が減少しやすいため、日々の食事でしっかり補うことが大切です!
カロリー管理や生活習慣病の予防に、エビは魅力的だと思いませんか?
低脂肪
エビは脂質が少なく、ヘルシーな食材です。体重やコレステロールが気になる場合にも最適!
ビタミン・ミネラル
エビは、ビタミンB12、セレン、亜鉛なども豊富です。これらは、エネルギー代謝の促進、免疫機能の強化、皮膚や髪の健康維持にも役立つ大切な栄養素!中高年層にとって重要なサポートとなります。
バランスよく効果的に摂取する方法
📌 1. 高タンパクを活かすなら「ビタミンB6・クエン酸」とセット!
エビのたんぱく質を効率よく体に吸収させるには、「ビタミンB6」や「クエン酸」を含む食材と組み合わせる と効果的!
💡 おすすめの食べ方
✅ エビ+ピーマン・パプリカ(ビタミンB6) → たんぱく質の代謝をサポート
✅ エビ+レモンや酢(クエン酸) → 胃酸の分泌を促し、消化吸収を助ける
▶ 具体例:「エビとパプリカのレモン炒め」
ピーマンやパプリカと一緒に炒め、仕上げにレモンを絞ると、たんぱく質の吸収率アップ!
📌 2. アスタキサンチンを活かすなら「良質な脂質」と組み合わせる!
アスタキサンチンは 「脂溶性」 のため、油と一緒に摂ると吸収率がUP します!
💡 おすすめの食べ方 ✅ エビ+オリーブオイル・ごま油・アボカド(良質な脂質) → アスタキサンチンの吸収率UP!
✅ エビチリ(豆板醤・甜面醤+ごま油) → 風味と栄養を同時に引き出す
▶ 具体例:「エビのアボカドサラダ」
オリーブオイルを使ったドレッシングをかけると、アスタキサンチンをしっかり吸収できる!
📌 3. ビタミン・ミネラルを活かすなら「亜鉛・セレン・ビタミンC」を意識!
エビに含まれる 「セレン」「亜鉛」「ビタミンB12」 は、免疫力強化・エネルギー代謝向上 に役立ちますが、吸収を助ける成分 を意識するとさらに効果的!
💡 おすすめの食べ方 ✅ エビ+キャベツ・ブロッコリー(ビタミンC) → 亜鉛の吸収を促進
✅ エビ+キノコ類(セレンが豊富) → 抗酸化作用UP
▶ 具体例:「エビとブロッコリーのにんにく炒め」
ビタミンC豊富なブロッコリーと炒めると、免疫力UP&代謝をサポート!

この栄養バランスを意識した「ヘルシー&満足感のあるエビチリ」を、最後に紹介します!
冷凍エビの添加物解説
冷凍エビに添加物が使われる理由
冷凍エビは 変色・食感・保存期間の向上 のため、加工の段階でいくつかの添加物が使われることが多いです。
特に使用頻度が高いのは、酸化防止剤・pH調整剤・リン酸塩など。
では、それぞれの目的と役割を詳しく見ていきましょう。
📌 冷凍エビに使用される主な添加物
| 添加物 | 目的 | 使用される理由 |
|---|---|---|
| 酸化防止剤(亜硫酸塩など) | 変色防止 | エビの黒変(メラニン生成)を防ぎ、見た目を保つため。 |
| pH調整剤(クエン酸、リン酸塩など) | 食感の維持・品質保持 | エビの身をぷりぷりに保ち、酸性やアルカリ性を調整する。 |
| リン酸塩(ポリリン酸ナトリウム、ピロリン酸ナトリウムなど) | 保水性向上 | エビの水分を保持し、ジューシーさを維持する。重量増加の目的も。 |
| 漂白剤(次亜硫酸ナトリウムなど) | 色の保持・黒変防止 | エビの黒ずみを防ぐために使われることがある。 |
| グルコン酸ナトリウム | 変色防止・保存性向上 | pHを調整し、変色や品質劣化を防ぐ。 |
| アスコルビン酸(ビタミンC) | 酸化防止 | 酸化による変色を防ぎ、鮮度を維持する。 |
| ソルビン酸カリウム | 防腐剤 | 微生物の増殖を抑え、保存期間を延ばす。 |
😮 これらの添加物、安全性はどうなの?
一般的に使用されているものの、一部には 「日常的に摂取する場合や食べ合わせの影響が未解明」 なものもあります。
例えば…
- 酸化防止剤(亜硫酸塩) → 一部の人にアレルギーの可能性
- リン酸塩(ポリリン酸ナトリウム) → 摂りすぎはカルシウムの吸収を妨げる可能性
- 漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム) → 使用量は管理されているが、一部の国では制限あり
「すぐに健康に悪影響が出るわけではないが、長期間にわたる摂取についても慎重に考えるべき」という意見もあります。
そのため、「できるだけ無添加のものを選びたい」と考える方も増えているようです。
では、自然なエビを選ぶことでどんなメリットがあるのでしょうか?
次章では、そのポイントを解説していきます。
無添加にこだわりたい場合の入手法
原材料欄をチェック → 「エビ、食塩」のみのものがあるとよいですが、なかなか見つからないときはこのような入手方法を検討しています。
1. 鮮魚コーナー 魚介類売り場の生鮮ならば添加物の心配はありません。むきエビは一部酸化防止剤が使われていることがありますので、殻付きのものを選ぶとよいです。
2. 生協(コープ)での購入 生協では、添加物を使用していない冷凍エビが取り扱われています。最寄りの店舗で取り扱い状況を確認してみてるといいです。
3. オンラインショップの利用 インターネット上の食品専門店や大手通販サイトでは、無添加の冷凍エビが販売されています。
4.業務スーパー・卸系スーパー 特に自然食品・オーガニック系に強い店舗には取り扱いがある可能性があります。
商流の都合で無添加は店頭から消えやすい?
スーパーで無添加の商品を見つけても、しばらくすると消えてしまうことがあります。
無添加食品は価格が高くなりやすく、売れにくい傾向があり、商売として成り立たないと取扱終了になるケースが多いからです。
この傾向は無添加エビにも当てはまり、「やっと見つけた無添加エビが消えてしまった…」という経験をされた方もいるかもしれません。

おーも以前はイトーヨーカドーの無添加冷凍エビ(原材料がエビと食塩のみ)の商品を愛用していましたが、最近は見かけなくなってしまいました…
最初に紹介したルートだと比較的長く入手可能な場合が多いのでおすすめです。
絶品!エビチリのレシピ紹介
エビの栄養をしっかり摂りながら、パンチのある味わいを楽しめるエビチリ。
基本レシピの豆板醤の代わりに、豆鼓醤(トウチジャン)と甜面醤(テンメンジャン)を使うことで、よりコクと深みが増します!
さらに、ニンニク&ショウガを加えることで、風味とパンチもUP!
味もしっかり&ボリュームも出るので、ガッツリ食べたい日のおかずにもぴったり! ぜひ試してみてください。
【材料】(2人前)
| 材料 | 分量(2人分) |
|---|
| むきエビ | 150~200g |
| 片栗粉(エビの下処理用) | 小さじ1 |
| 長ネギ | 1/2本(みじん切り) |
| 玉ねぎ | 1/4個(みじん切り) |
| ニンジン | 1/4本(細切り) |
| ピーマン or パプリカ | 1/2個(細切り) |
| ニンニク(すりおろし or みじん切り) | 小さじ1/2 |
| ショウガ(すりおろし or みじん切り) | 小さじ1/2 |
| 調味料 | 分量(2人分) |
|---|
| 豆板醤 | 小さじ1 |
| ケチャップ | 大さじ2 |
| 砂糖 or オリゴ糖 | 小さじ1 |
| しょうゆ | 小さじ1 |
| 鶏ガラスープの素(粉末) | 小さじ1/2 |
| 水 | 50ml |
| 片栗粉(水溶き用) | 小さじ1(+水小さじ2で溶く) |
| ごま油(仕上げ用) | 小さじ1 |
📌 豆板醤を豆鼓醤&甜面醤に変更する場合
- 豆板醤 (小さじ1) →
豆鼓醤(小さじ1/2)+甜面醤(小さじ1) に置き換えるとコク深い仕上がりに!
🍳 作り方
1️⃣ エビの下処理
- エビに片栗粉をまぶし、揉み込んでから流水でよく洗う(臭み取り&プリプリ食感アップ)。
- キッチンペーパーで水気をしっかり拭き取る。
2️⃣ エビを炒める
- フライパンに油を熱し、中火でエビを炒める。
- 軽く焼き色がついたら、一旦皿に取り出す。
3️⃣ 野菜を炒める
- フライパンに油を足し、ニンニク・しょうが・長ネギを炒める。
- 香りがでたら玉ねぎ・ニンジン・ピーマンも加える。
- 野菜がしんなりしたら、豆板醤を加えて炒める。
4️⃣ 調味料を加えて仕上げ
- 豆板醤・ケチャップ・砂糖・しょうゆ・鶏ガラスープの素・水を全体になじませる。
- 炒めたエビを戻し、水溶き片栗粉でとろみをつけ、全体をよく絡める。
5️⃣ 完成!
- お皿に盛り付けて、熱いうちにどうぞ!

アスタキサンチンは脂溶性なので油を使ったレシピとの相性抜群。トマトケチャップも無添加を選ぶとより健康的。豆板醤のパンチが効いていて、がっつり食べたい日でもヘルシーながら満足感を得られます。
まとめ
この記事のまとめです!
1️⃣ エビの健康メリットの総括
- 低脂肪・高タンパクでヘルシー
- アスタキサンチンによる抗酸化作用
- ビタミン・ミネラル豊富で代謝&免疫をサポート
2️⃣ 添加物のポイント
- 冷凍エビには品質保持のための添加物が使用されることが多い
- 日常的な摂取や長期的な影響については慎重に考えたい
- できるだけ無添加を選びたい人向けの入手方法も紹介
3️⃣ 効果的な食べ方&レシピ
- エビの栄養を最大限活かす食べ合わせのコツ
- 甜面醤&豆鼓醤でコクを増した「こだわりエビチリ」レシピ
エビは栄養豊富で健康的な食材です。
選び方や調理法を工夫して、美味しく&安心して楽しもう!