スーパーの「見切り品」、お好きですか?
おーは大好きです。おトクに買えたラッキー感がたまりません。
でも商品によっては買って損するものもあります。
とくに生鮮品は要注意。
肉や魚でパックの中で赤い汁が溜まっているものを見たことはありませんか?
あの汁が出ているものは選ばないで!
あの赤い汁の正体は「ドリップ」といって、菌の増殖・栄養価の低下・食感の悪化が進行しているサインです。オトクに買えたつもりでも、健康リスクを高めてしまっては元も子もありません!
この記事ではドリップの危険性と、生鮮食品を選ぶときのポイントを詳しく解説します。
ドリップが危険な理由
ドリップの正体は、食材の水分と血が混ざったもの。
雑菌が繁殖しやすい環境となるので、注意が必要です。
売り場では、保冷の利いたコーナーに陳列されているのでまだ問題ありませんが、買い物かごに入れると常温になりますよね。
ここからじわじわと劣化が進みます。
店内を移動しながら買い物を続けて、お会計後に帰宅、冷蔵庫に保存するまで、かなりの時間がかかります。ドリップが出た食材は、この時間でさらに傷みやすくなります。
目に見えなくても劣化が進行中
鮮度のよい生鮮品であっても、常温にさらされる時間が長いほど、腐敗が加速します。
食品衛生学的には、10℃を超えると細菌が増えやすくなり、特に30~40℃では急激に繁殖するとされています。夏の車内などはかなり危険な環境ですね!
ドリップの中には、もうすでに細菌がいます。水分+食材(タンパク質)がエサになるため、常温の状態だとドリップのない状態と比較すると、かなりリスクは高いとされています。
詳しくは、農林水産省が提供する食品安全情報(公式サイト)をご確認ください。
まさか買い物かごの中でそんなことが起きているとは、なかなか想像したくありませんね!
赤くなければ安全?白身魚、実は…
お肉や赤身の魚のドリップは赤やピンクなので目立ちますが、タラなどの白身魚のドリップは「ちょっと水が出てるだけ?」みたいに感じるかもしれません。
でも本当は白身魚のほうが細菌リスクが高いんです!
白身魚のドリップが赤くないのは、血にヘモグロビン(赤い色素)が少ないから。
白身魚のドリップと赤いドリップの違い
赤いドリップ(肉・赤身魚)の特徴
- ヘモグロビン(Hb)やミオグロビン(Mb)が含まれるため赤色。
- 血液由来の成分が多く、酸化しやすい。
白身魚のドリップの特徴
- ヘモグロビンが少ないため透明または薄い白色。
- 代わりに、腐敗を進行させやすい物質(トリメチルアミンオキシド(TMAO))が含まれる。
- 腐敗するとトリメチルアミン(TMA)に変化し、強い生臭さを放つ。
- 結果的に腐敗スピードが速く、赤身魚より雑菌繁殖リスクが高い可能性も。
見た目のインパクトによらず、赤いドリップよりも傷んでいることに気づきにくいため、より注意が必要です。
貝類のドリップも見逃せない!
アサリ・ハマグリ・ホタテ・シジミ・ムール貝などの貝類もドリップが出ていることがあります。
貝はパックされる時点で生きているので、少量のドリップにはアミノ酸などのうまみ成分が溶け出しています。生体反応である点がお肉や魚とちょっと違う点です。
とはいえドリップの性質上、リスクは肉や魚の場合と変わりません。汁が隅にたまるくらいの量だと鮮度が心配です。ドリップが少ないものでも、なるべく早めに食べるのがベスト!
判断の目安としては、白濁が進んでいたら避けたほうが無難です。
加熱すれば細菌は大丈夫!?
「細菌が増えても加熱すれば安全なのでは?」
と思うかもしれません。ただ菌がたくさんいる場合、加熱が不十分だと一部の菌が生き残るリスクも高くなります。また腐敗自体は進んでしまうため、どうしても風味や食感は落ちてしまいます。
それに加熱すれば細菌は死滅するものの、一部の菌が作り出した毒素は熱に強く、加熱しても分解されない場合があります。さすがにここまで劣化が進んでいたらニオイで気付けますが…。

無理に使ったりはせず、酸っぱい臭いや鼻を刺すような異臭がするときは迷わず廃棄してくださいね!
大切な栄養素も減ってしまっているので、お安く買えてもメリットが少ないと思いませんか?
安物買いの罠を避けろ!新鮮なものを選ぶ利点
ドリップがなければ見切り品もあり!
見切り品でもドリップがなく、鮮度が保たれていそうなものなら比較的安心です。
多少栄養価は落ちているかもしれませんが、すぐに調理すればお財布にも優しくて食品ロスにも貢献でき、とってもエコ!
買う場合も、消費期限は短いため、すぐに使わないなら下処理だけして冷凍庫で保管するようにしましょう。ドリップがなければひとまず鮮度は保ちやすいものの、早めに使うようにするとよいです。

おーは状態のよい見切り品を見つけると、まとめ買いして、小分けで冷凍保存しています。
生鮮を安全に冷蔵庫まで移動する工夫を
生鮮食品は、なるべく低温状態をキープするのが鮮度を保つコツです!
素早く買い物をすませればそれほど深刻なダメージにはなりにくいですが、万全を来すなら、
販売コーナー(低温)→買い物かごの中(常温)→帰宅中(常温~高温)→冷蔵庫(低温)
「常温」「高温」の区間を4℃前後に抑える工夫をするのがベストな対策です。
店内専用保冷バックの活用
買い物かごの中に入れるときは、店内専用の保冷バックを使用すると安心です。
店内で買い物を続ける間やレジでの時間も劣化を防いでくれます。店内で貸し出ししているスーパーもありますが、貸し出しサービスがない場合もあるので、普段使いできるマイ保冷バッグを持っておくと安心です。
帰宅時は保冷材やクーラーボックスで鮮度をキープ
保冷材やクーラーボックスで、帰宅時までしっかり保冷するのも大切です。
特に夏場は、帰宅したらドリップが発生していた、なんてことも起きやすいので要注意です!

保冷材などの備えがないときも、生鮮食品と冷凍食品をくっつけておけば相乗効果で低温キープしやすいです
自宅に着いたら、すぐに冷蔵庫へ。
ドリップのない生鮮食品なら、これでかなり鮮度をキープできますよ!
安全で便利な保存方法
肉や魚は消費期限内に使う予定があれば、チルドルームで保存するのが最適です。
もしすぐに調理しない場合は、はやめに冷凍庫に入れるのがオススメ。
魚の冷凍方法
切り身
買ってきたまま冷凍庫にポイ!が一番楽です(笑)
丁寧に管理するならフリーザーバックに移して、なるべく空気に触れないようにしたほうが鮮度も持ちます。冷凍庫内のスペースも節約できるので、お好みで!
一尾(捌く)
自分で3枚おろしにした場合などは、水気をキッチンペーパーでしっかりふき取るひと手間が鮮度を保つコツです。痛みの原因になりやすい内臓の取り残しがないかも、よくチェックしてください。
ラップやフリーザーパックで小分け保存。魚種に関係なく、1か月程度は保存可能です。
貝の冷凍方法
冷凍OKの貝
アサリ・シジミ・ハマグリ
アサリ・シジミ・ハマグリなどは、よく砂抜きをしてからフリーザーパックで保存を。
調理時は凍ったまま加熱でOK。凍らせると細胞が破壊され、うま味もUPするのでメリットだらけ!
ホタテ・カキ
生でも加熱後でも冷凍可能です。加熱後は汁ごとフリーザーパックに入れて丸ごと保存OKです。
冷凍はやや食感は落ちますが、風味は維持しやすいのでダシ利用もいいですね。
ムール貝・アワビ
加熱後の冷凍がおすすめです。
こちらもスープごとフリーザーパックで保存します。ムール貝は殻ごと、アワビはスライスして保存も可です。
こんな貝は冷凍NG!
🚫 二枚貝(ハマグリ・アサリなど)のドリップが多い状態で冷凍すると、雑菌が増えやすく危険!
🚫 貝の状態が悪い(死んでいる)と、冷凍しても味が落ちる!
🚫 調理済みでも水分が多すぎる場合、解凍時にベチャッとしてしまう!
肉の冷凍方法
使いやすくカットしてから
あらかじめ使うときのサイズで切ってから冷凍すると調理するとき便利です。
魚の切り身同様、買ってきたままポイ!が楽なのですが、薄切りロースでさえ凍ったままの肉を包丁で切るのはかなり大変です(笑)
切ってから小分けにして保存しておけば、使いたいとき鍋やフライパンに直行できるので、タイパも抜群です。
下味をつけて保存
しょうゆなど下味をつけてから冷凍保存するのも時短になりますね!
ただ、味が染みやすいもの・向かないものもあるのでケースバイケース。これについてはいずれ別の記事で紹介できればと思います。
鶏むね肉の冷凍はタイパ最強
最後に。お肉の冷凍なら鶏むね肉が断然オススメ!
理由は使いやすさ。普通に調理するときもですが、加熱調理しても肉同士がくっつきにくい特徴があります。この特徴は、冷凍・解凍状態の場合も変わりません。
冷凍庫からフライパン直行 → つきっきりでほぐす必要なく、ほったらかしでOK
なので、調理の手間がぐっと減りますよ!

鶏むね肉はダイエットや筋トレにも最適なので、別の記事でも紹介しますね!
まとめ:ドリップに注意し、安全に食品を管理しよう!
ドリップは、生鮮食品の鮮度低下のサインであり、雑菌の繁殖リスクや栄養価の低下を招く要因になります。見切り品を選ぶ際や、食材を保存する際には、ドリップのあるなしをしっかりチェックし、安全に管理しましょう。
✅ ドリップには細菌が繁殖しやすい環境が整っている!
✅ 買い物時に保冷バッグ等を活用し、できるだけ低温を維持する工夫を!
✅ すぐに使わない場合は、冷凍保存で購入後のドリップも最小限に!
この記事が、より安全でおいしい食生活を送るお手伝いになれば幸いです。
あなたの工夫やこの記事への感想などをコメントでもらえると、励みになりとても嬉しいです!
ではまた!
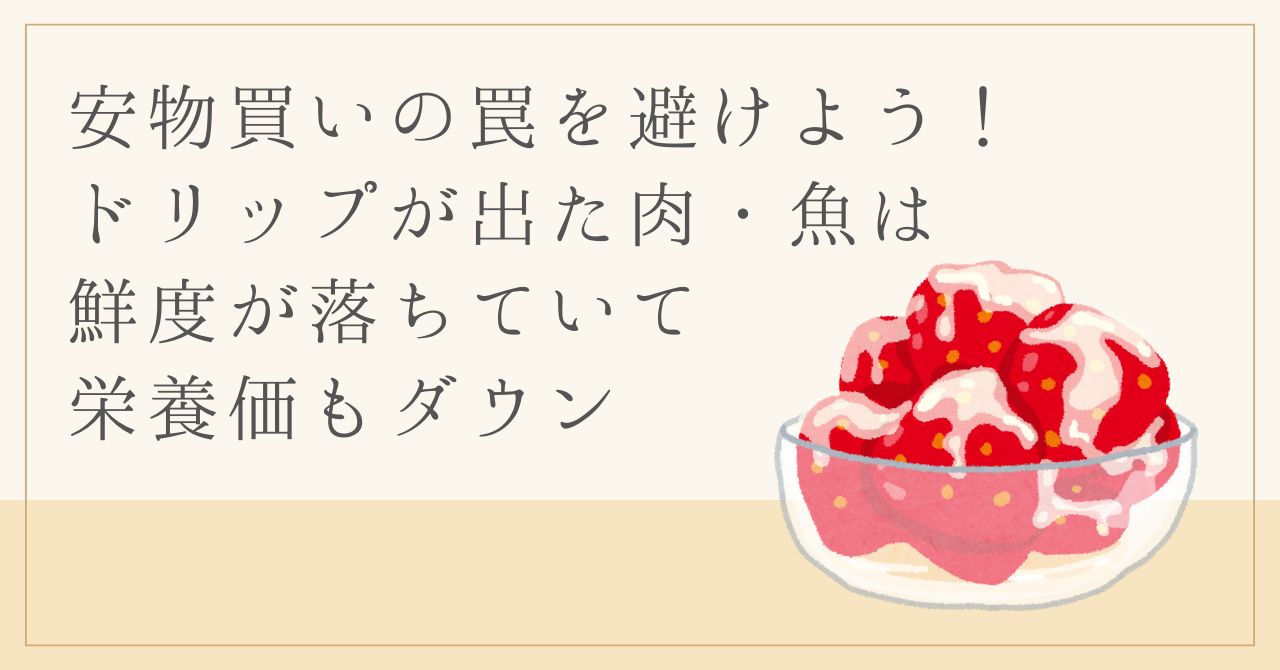
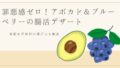
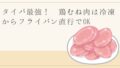
コメント