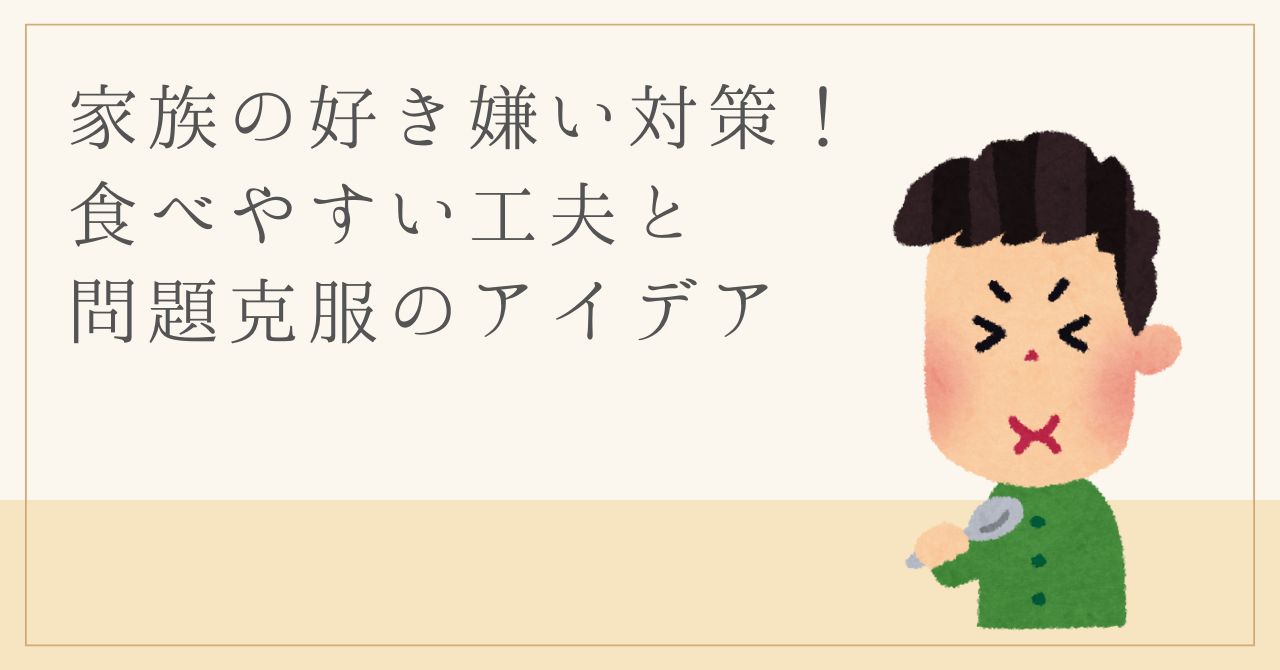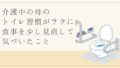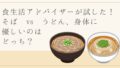家族の好き嫌い問題は、多くの家庭で頭を悩ませるテーマです。
「子どもはトマトが苦手」「夫はネバネバしたものが嫌い」「親は脂っこい料理を避けたい」など、一人ひとりの好みが異なり、食事の準備が大変になることも。

こんにちわ。食生活アドバイザーのおーです。
作り手が家族の好みに合わせようとすればするほど、料理の負担が増え、ストレスを感じやすくなるかもしれません。かといって、無理に嫌いな食べ物を食べさせようとすると、家族の間で不満が生じ、角が立ってしまうのも心配。
こんなジレンマに陥ると、食卓は楽しい場であるはずなのに、食事のたびに気を遣うことが増えてしまいがち。家族の健康を考えるからこそ、「どうにかして食べさせるべきか?」と悩む場面もあるかもしれません。
では、好き嫌いの問題にどう向き合い、家族の健康と食の楽しさを両立させるにはどうすればよいのでしょうか?
本記事では、好き嫌いの理由を整理し、食べやすくする工夫を試したうえで、それでも難しい場合に栄養を補う方法について解説します。一緒に考えてみましょう。
なぜ嫌いなのか? 好き嫌いの理由を知る
ある日、子どもに「ピーマン食べてみたら?」と言ったら、即答で「やだ!」
「どうして?」と聞くと、「苦いから!」 とのこと。
「なるほど、それなら苦みを和らげれば食べられるかも?」と思い、チーズと合わせてみたら、意外と食べてくれた!
よくあるエピソードですが、実は、好き嫌いには理由があることを把握するのは大切なことです。
「ピーマンが嫌い」と一言で言っても、「苦みがダメなのか?」「食感が嫌なのか?」を知るだけで、工夫の方法が見えてきます。
よくある嫌いな理由の例
食感が苦手(ネバネバ・シャキシャキ・トロトロ・プリプリなど)

口に入れた瞬間の感触がイヤ!

食感が苦手なら →「ペーストやスープにする」など、食感を変えると食べやすくなるかも
見た目が苦手(緑色の野菜・血や内臓系・魚の鱗や目・ぶよぶよ・ドロドロ)

「見た瞬間にダメ!」

見た目が苦手なら →「原形を残さず刻んで調理したり、カレーや炒め物など色の強い料理に混ぜる」と、見た目が気になりにくいかも
食わず嫌い(決めつけ・思い込み)

「〇〇だから絶対おいしくない!」

思い込みが原因なら →「まずは好きな味付けで試してみる」と、意外と食べられることもあるかも
ニオイが苦手(発酵臭・油脂・乳製品・香草・スパイス)

「鼻にツンと来る!」

ニオイが苦手なら →「加熱して香りを飛ばしたり、ゴマ油やショウガなど香りの強い調味料と組み合わせる」と気になりにくいかも
味が苦手(苦い・酸っぱい・しょっぱい・辛い・甘い)

「舌に残る感じが無理!」

味が苦手なら →「チーズやカレー風味など、はっきりした味付けに」すると、苦手な風味が和らぐかも
食べやすくする工夫を試したが…
ある日、家族の好き嫌いをどうにか克服させようと頑張ってみた。
ピーマンが嫌いな子どもにはチーズと合わせてみたり、魚のニオイが苦手な家族にはショウガを効かせてみたり。
「ほら、これなら食べられるんじゃない?」 と工夫した料理を出してみた。
結果は…?
意外と食べてくれたものもあったし、「やっぱりダメ!」というものもあった。
食べてくれた時は嬉しかったけれど、食べてくれない時はちょっと落ち込む。
「こんなに工夫しても、どうしてもダメなものってあるんだな…」

こんなふうに思い悩んでしまうこともあるかもしれません。
でも、少しだけ考え方を変えてみてはどうでしょう。
そもそも全部食べなくてもいいのでは?
「でも、そんなに無理に食べさせる必要があるのかな?」
こう疑問に思うことは自然なことだと思います。
好き嫌いをなくすことにこだわるあまり、「食べなさい!」と強く言ってしまって、食事の雰囲気がピリピリしてしまった。
これって本当に良いことでしょうか?
よく考えてみると「特定の食材を食べなくても、栄養は補える」 ことが多いことに気づくはずです。
- 鉄分はレバーだけじゃなく、ほうれん草や大豆食品でも摂れる。
- 乳製品が苦手でも、小魚やナッツ類からカルシウムを補える。
- 食物繊維なら、ゴボウが苦手でも、納豆や枝豆、海藻類からも摂れる。
- DHAが豊富な魚が苦手なら、くるみやアマニ油などから補うことも可能。
「栄養さえ取れれば、食べられないものがあっても大丈夫なのかも?」
そう考えると、少し気持ちが楽になりませんか?
家族の好き嫌いとどう向き合うか。ちょっと視点を変えてみると、無理しなくても解決できる方法が見えてくるかもしれないません。次章では、この考え方について深堀してみましょう。
好き嫌いは工夫でカバーできる!栄養バランスを整える方法
「好き嫌いなく、なんでも食べる!」
そう思っても、現実はなかなかそうはいかないものですよね。
でも大丈夫。栄養素はさまざまな食品に含まれており、特定の食材を食べなくても健康を維持することは可能です。
今回は、よくある嫌いな食材とその代替食品をまとめました。
健康維持に役立つ!代表的な苦手食品の置き換えリスト
| 品目 | 主な栄養素 | 説明 | 補える食品 |
|---|---|---|---|
| ピーマン | ビタミンC | 強力な抗酸化作用を持ち、皮膚や血管の老化を防ぎ、免疫力を高める効果が期待できます。コラーゲンの生成を助け、シミやシワの予防にも役立ちます。 | パプリカ、ブロッコリー、いちご、キウイ、レモン、アセロラ、芽キャベツ、菜の花 |
| 牛乳 | カルシウム | 骨や歯を丈夫にし、骨粗鬆症の予防に役立ちます。神経の興奮を鎮め、精神安定にも効果があります。筋肉の収縮をスムーズにし、成長期の子供の骨の成長を助けます。吸収にはビタミンDが不可欠です。 | 豆腐、小魚(しらす、煮干し)、チーズ、ナッツ(アーモンド、くるみ)、ヨーグルト、ひじき、モロヘイヤ、大豆、豆乳 |
| トマト | リコピン | 強力な抗酸化作用で、活性酸素を除去し、動脈硬化やがんのリスクを低減します。紫外線から肌を守り、美白効果も期待できます。加熱することで吸収率がアップします。 | 赤ピーマン、スイカ、ピンクグレープフルーツ、柿、グァバ、人参、パプリカ |
| レバー | 鉄分 | 赤血球のヘモグロビンの材料となり、全身への酸素供給を助けます。貧血を予防し、疲労回復にも効果があります。ビタミンCと一緒に摂ることで、鉄分の吸収率が向上します。 | ほうれん草、豆腐、ひじき、あさり、カキ、海苔、小松菜、プルーン、大豆、切り干し大根 |
| ゴボウ | 食物繊維 | 腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整えます。便秘を解消し、有害物質の排出を促します。血糖値の急上昇を抑え、コレステロール値を下げる効果も期待できます。水溶性食物繊維と不溶性食物繊維をバランス良く摂取することが重要です。 | きのこ類(しいたけ、えのき、しめじ)、海藻(わかめ、昆布、もずく)、オートミール、玄米、麦、豆類、アボカド、ブロッコリー、キャベツ |
| 魚全般 | DHA・EPA | 脳の活性化、認知機能の維持に役立ちます。血液をサラサラにし、血栓予防、動脈硬化予防に効果があります。炎症を抑え、アレルギー症状の緩和も期待できます。特に青魚に豊富に含まれています。 | アマニ油、くるみ、えごま油、亜麻仁油、イワシ、サバ、サンマ、マグロ、ブリ、サーモン |
| セロリ | フラボノイド | 活性酸素を除去し、動脈硬化やがんのリスクを低減します。血圧を下げる効果や、炎症を抑える効果も期待できます。独特の香りは精神安定作用があります。 | ブルーベリー、玉ねぎ、ブロッコリー、そば、リンゴ、グレープフルーツ、赤ワイン、緑茶、大豆 |
| ニンジン | β-カロテン | 体内でビタミンAに変換され、皮膚や粘膜を保護し、免疫力を高めます。目の健康を維持し、視力低下を防ぎます。抗酸化作用により、老化を遅らせる効果も期待できます。 | かぼちゃ、さつまいも、ほうれん草、小松菜、モロヘイヤ、春菊、トマト、マンゴー |
| ブロッコリー | ビタミンK | 血液凝固を助け、止血作用があります。骨の形成を促し、骨粗鬆症の予防に役立ちます。ビタミンDと協力してカルシウムの吸収を助けます。 | ほうれん草、小松菜、春菊、ニラ、キャベツ、レタス、パセリ、抹茶、海苔 |
| ネギ | アリシン | 強い抗菌作用があり、風邪やインフルエンザの予防に役立ちます。血行を促進し、体を温める効果があります。ビタミンB1の吸収を助け、疲労回復を促します。 | ニンニク、玉ねぎ、ニラ、らっきょう、浅葱、茗荷 |
| シイタケ | ビタミンD | カルシウムの吸収を助け、骨を丈夫にします。免疫力を高め、感染症予防に役立ちます。がん細胞の増殖を抑制する効果も期待できます。日光に当てることでビタミンDの量が増加します。 | サーモン、卵黄、イワシ、サンマ、キノコ類、メカジキ、マス、カレイ |
| オクラ | ムチン | 胃の粘膜を保護し、胃潰瘍や胃炎の予防に役立ちます。消化を助け、栄養吸収を促進します。整腸作用があり、便秘解消にも効果があります。 | 山芋、なめこ、里芋、レンコン、モロヘイヤ、明日葉、ツルムラサキ |
| 卵 | タンパク質 | 筋肉、臓器、皮膚、髪など、体を作る上で最も重要な栄養素です。免疫細胞の材料となり、免疫力向上にも役立ちます。必須アミノ酸をバランス良く含んでいます。 | 肉、大豆製品、魚介類、乳製品、豆腐、納豆、鶏むね肉、ささみ、卵白 |
| チーズ | 発酵ペプチド | 腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整えます。消化吸収を助け、免疫力向上にも役立ちます。血圧を下げる効果や、精神安定効果も期待できます。カルシウムも豊富に含んでいます。 | ヨーグルト、発酵食品(味噌、醤油、納豆、キムチ、漬物)、サワークリーム、ケフィア、コンブチャ |
【出典元】本記事の情報は、文部科学省「食品成分データベース」( https://fooddb.mext.go.jp/ ) を参考に、各食品の一般的な栄養成分をまとめたものです。(2025年2月28日閲覧)
注意点:
- 各食品の栄養成分含有量は、品種や栽培方法、調理方法などによって変動する可能性があります。
- 特定の食品に対するアレルギーがある場合は、摂取を避けてください。
- バランスの取れた食事を心がけることが重要です。

とはいえ、特定の食品からしかメリットを得られないものもあります。
次はそれらについても考えてみましょう。
代替できない機能性成分もある
ビタミン・ミネラルなどの栄養素は代替可能ですが、納豆のナットウキナーゼのように、一部の機能性成分は特定の食品からしか摂取できなかったり、または含有量が突出していたりします。
こうした栄養素は、できるだけ食事から摂取できるように工夫するのが理想的です。
| 品目 | 成分名 | 成分の働き | 備考 |
|---|---|---|---|
| 納豆 | ナットウキナーゼ | 納豆菌がつくり出す酵素で、血栓を溶解する作用(線溶作用)があります。血栓の主成分であるフィブリンを分解し、血液をサラサラにする効果が期待できます。血圧を下げる効果や、動脈硬化を予防する効果も研究されています。 | ナットウキナーゼは納豆に特有の成分であり、他の食品では補えません。ただし、他の食品から血栓予防に役立つ成分を摂取することはできます。 |
| ワサビ | 6-MITC(6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネート) | 強い抗菌作用があり、食中毒予防に役立ちます。抗酸化作用や抗炎症作用も確認されており、がん予防や認知機能改善への効果も研究されています。 | アブラナ科の野菜(キャベツ、ブロッコリーなど)にもわずかに含まれますが、ワサビに特に多く含まれています。 |
| お茶(緑茶) | カテキン | 強い抗酸化作用があり、活性酸素を除去し、老化を抑制する効果が期待できます。抗菌作用や抗ウイルス作用、血糖値上昇抑制作用、コレステロール低下作用なども知られています。 | 他の植物にもポリフェノールは含まれますが、緑茶に特に豊富に含まれるカテキンは、その種類と量において特筆されます。 |
| 紫色の野菜(ナス) | アントシアニン | 強い抗酸化作用があり、活性酸素を除去し、目の疲労を軽減する効果や、視力改善効果が期待できます。毛細血管を保護する作用や、血圧を下げる効果も報告されています。 | 他の色の野菜や果物にもアントシアニンは含まれますが、紫色の野菜に特に多く含まれています。 |
| カカオ(チョコレート) | カカオポリフェノール | 強い抗酸化作用があり、活性酸素を除去し、血管を拡張して血圧を下げる効果や、動脈硬化を予防する効果が期待できます。脳の血流を改善し、認知機能を高める効果も研究されています。 | 他の食品にもポリフェノールは含まれますが、カカオ豆に特に豊富に含まれるカカオポリフェノールは、その種類と量において特筆されます。 |
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から出典
相手を変えず、発想を変えて向き合う
悩んだら見方を変える
好き嫌いの問題に直面すると、多くの人が「どうにかして食べさせなければ」と考えがちです。
しかし、無理に克服させようとすることで、食卓がストレスの場になり、家族の関係に悪影響を及ぼすこともあります。
相手を変えるのは簡単ではありません。ましてや嗜好となるとなおさらです。でも、自分の発想を少し変えてみるだけで、状況が驚くほど楽になることもあります。
「どうすれば食べてくれるの?」から一歩踏み込んで、「これが苦手でも、こっちで代替すればいいかも」という視点に切り替えれば、気持ちもスッと楽になります。
食べやすい工夫をして、それでもダメなら無理に食べさせようとしない余裕があれば、健全で楽しい食生活を送れると思います。
好き嫌い問題の対応ポイント(まとめ)

おーの考える「好き嫌いへの対応で優先すべきこと」は、以下の通りです。
 栄養バランスを確保する
栄養バランスを確保する
「特定の食材にこだわらず、栄養素を補うことが大切」
苦手な食材があっても、同じ栄養素を含む別の食品で補えれば家族の健康を守ることができます。
食事の役割のひとつは「栄養を摂ること」。健康を維持するために「何をどう食べるか」を自由に選べば、必要以上に悩むことはなくなるかもしれません。
 食べることを楽しめる環境を作る
食べることを楽しめる環境を作る
「好き嫌いは良くないから食べなきゃ」と思うと、食事そのものが負担になりがちです。コミュニケーションや楽しみを邪魔しない範囲の工夫は試してみる価値は十分にあります。
 食の好みは時間とともに変化する
食の好みは時間とともに変化する
味覚は年齢とともに変わることがあり、『昔は苦手だったのに、今は食べられる』というケースもよくあります。無理に急ぐ必要はなく、食べることをポジティブに楽しめる余裕のほうが大切かもしれません。
まとめ
好き嫌いの問題は、多くの人が「どうにかして食べられるようにしなければならない」と考えがちです。しかし、無理に解決しようとすれば、食事そのものがストレスになってしまうこともあります。
本記事では、視点を変えることで気持ちが楽になる方法について考えてきました。
 「工夫」の視点
「工夫」の視点
味や食感を調整したり、環境を整えたりすることで、食べやすくなることもあります。
また、食の好みは時間とともに変わるため、今食べられなくても気にしすぎる必要はありません。
だから、焦ることなく様子を見てみるのもよいかもしれませんね。
 「目的」の視点
「目的」の視点
食事の本質は、栄養を摂ることだけではなく、「楽しく食べること」にもあります。
無理に食べさせることよりも、家族全員がリラックスして食事を楽しめる状況のほうが良い食生活といえないでしょうか。
日々の食卓で「食べられる・食べられない」にとらわれず、「どうしたら食事をみんなで楽しめるか?」と視点を変えてみると、食の時間がもっと豊かになるかもしれません。