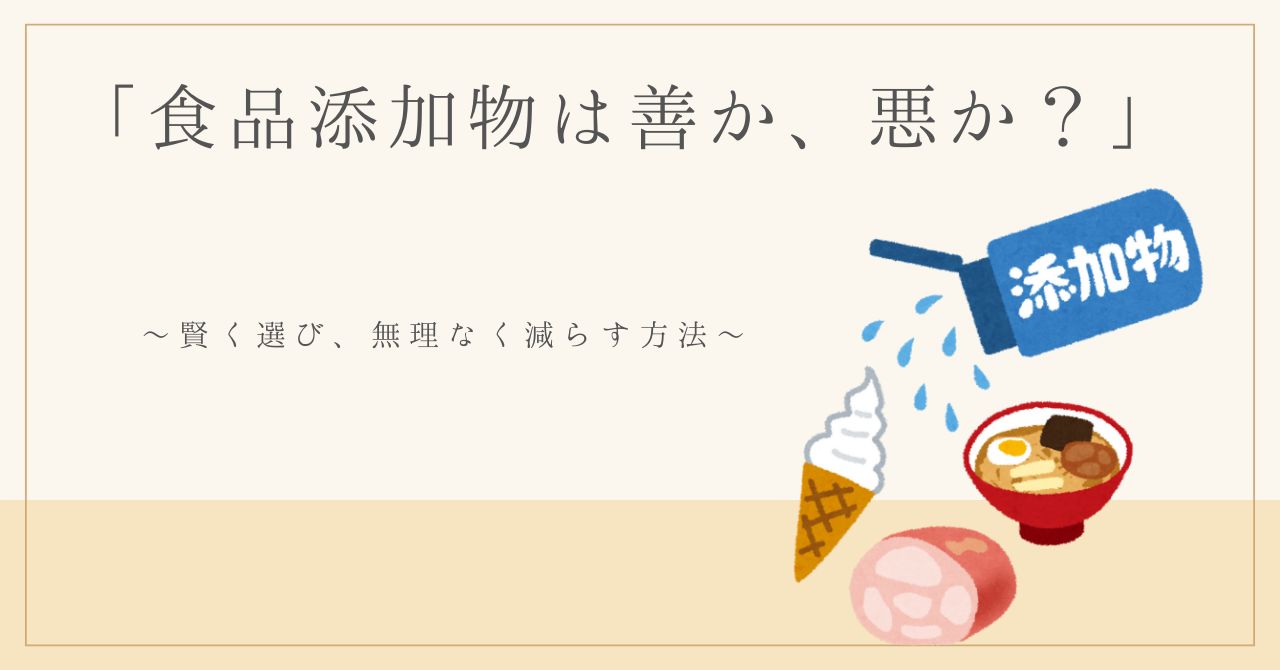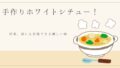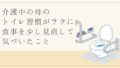「食品添加物は体に悪い」「無添加こそが正義」
健康志向の高まりの影響か、よくこんなフレーズを目にすることが増えました。でも、本当にそうなのでしょうか?

こんにちわ。食生活アドバイザーのおーです。
食材の品質維持や風味向上のため、私たちの食生活には多くの食品添加物が使われています。「何が入っているのか分からなくて不安…」と思うかもしれませんが、まずは 食品添加物とは何か? を正しく理解することが大切です。
食品添加物とは 天然物・化学合成物を問わず、食品に添加されるすべてのもの を指します。例えば、ビタミンC(酸化防止剤)やクエン酸(酸味料)も食品添加物の一種です。
また、食品添加物には 一日摂取許容量(ADI)の基準が設けられており、適量であれば健康への影響はほぼない とされています。そのため、基本的には「安全」と考えられます。
食生活アドバイザー試験でも基本知識として押さえておきたいポイントです。
食品添加物の使用は20世紀以降に拡大し、現在では日常的に摂取するのが一般的になっています。そのため、まだ歴史が浅く、化学合成された添加物の長期的な影響については、一部未解明の部分もあります。
また、安全性が確認されているものも多い一方で、注意が必要なものや、できるだけ避けた方がよいものもあります。では、私たちは実生活の中でどのような点に注意し、食品添加物と付き合っていけばいいでしょうか?
この記事では、食品添加物を「温度感別」に分類し、どこに気をつければよいかを整理し、実生活で無理なく添加物を減らす方法を紹介します。
食品添加物の考え方:「温度感別」で整理する
まずは基本!「原材料表示の見方を知ろう」
食品添加物に興味がある方も、これまであまり気にしてこなかった方も、まずは 『原材料表示の基本ルール』 を知っておくと、選び方のヒントになります。
食品添加物は、商品のラベルにある『原材料名』の部分で確認できます。最初に記載されているものほど含有量が多く、スラッシュ(/)以降が食品添加物の記載です。すべてを覚える必要はなく、表記がやたらに長いほど加工度が高い傾向がある、いう視点だけでも判断材料になります。
では、使用頻度の高い添加物には、どのようなものがあり、どのようなリスクがあるのでしょうか?
日本の食品添加物の数はどのくらい?
厚生労働省のホームページによると、『令和4年10月26日現在、日本の食品添加物の数は831品目(香料を含む)あります。』と公表されています。
出典:厚生労働省「Q4.食品添加物の海外の基準は日本よりも緩いのですか?」
数百種類もの食品添加物をひとつひとつ理解し、すべてを把握するのは現実的ではありません。
そこで、本記事では 使用頻度が高い添加物 にフォーカスし、それらを 健康リスクの観点から3つのレベル(低・中・高)に分類 することで、無理なく把握できる方法を提案します。
ざっくりでも方向性を把握しておけば、選びやすくなり、過度な不安を減らすことができます。
さっそく見ていきましょう!
比較的安全とされる添加物
 安全性が確認されており、適量であれば健康リスクが少ないもの。
安全性が確認されており、適量であれば健康リスクが少ないもの。
添加物としての歴史が比較的長いものや、自然由来または自然に近い物質などがこれにあたります。さまざまな原材料名の中に見かける代表的な例として、以下のような添加物が挙げられます。
▶ 例:
- クエン酸(酸味料):レモンなどに含まれる成分で、体内で代謝される
- ビタミンC(アスコルビン酸)(酸化防止剤):天然の抗酸化作用を持ち、食品の酸化を防ぐ
- 重曹(炭酸水素ナトリウム)(膨張剤):ベーキングパウダーの成分で、安全性が高い
これらの添加物は、過度に気にする必要はありませんが、知識として覚えておくと食品選びの参考になります。
注意が必要な添加物
 安全性は確認されているが、過剰摂取や体質によって影響が出る可能性があるもの。
安全性は確認されているが、過剰摂取や体質によって影響が出る可能性があるもの。
国の基準では安全な量が使用されており、通常の食事で過剰摂取になることは考えにくいとされています。しかし、日常的にさまざまな食品から摂取するうちに、不安を感じることもあるかもしれません。そういう場合は、無理のない範囲で控えるのもひとつの選択肢です。
▶ 例:
- ショートニング(加工油脂):一部にトランス脂肪酸を含み、心血管系への影響が指摘
- リン酸塩(結着剤):加工肉・チーズなどに含まれ、カルシウムの吸収を阻害する可能性
- 増粘多糖類(カラギナン):ゼリーやプリンなどに含まれ、一部で消化器系への影響が懸念
摂取頻度を抑えたり、加工度の低い食品を選ぶことで、自然と摂取量を減らすことができます。認識した上で、自分に合った選択をするのが現実的でしょう。
できるだけ避けたい添加物
 一部の研究で健康リスクが指摘され、海外では使用制限・禁止されているものなど
一部の研究で健康リスクが指摘され、海外では使用制限・禁止されているものなど
日本で使用されている食品添加物のなかには、このようなものもあります。国ごとの文化や風土、規制基準が異なるため、必ずしも一律に危険とは言い切れません。しかし、意識することで自主的な選択をすることは自分や家族の健康を守るためにも重要です。
▶ 例:
- アスパルテーム・アセスルファムK(人工甘味料):WHOが発がんリスクを指摘
- BHA・BHT(酸化防止剤):一部の国で発がん性の可能性が報告
- 赤色2号・赤色102号・黄色4号(合成着色料):EU・米国では使用禁止のものもありアレルギーや発がん性リスクが懸念
- 果糖ブドウ糖液糖(液体甘味料):血糖値を急上昇させ、糖尿病リスクを高める可能性
病気や疾患との直接的な因果関係が明確に証明されたわけではありません。ただこれらを含まない食品で食生活を組み立てることは十分可能なので、知識として持っておくのはメリットです。
補足:加工食品に多い「無機リン」の問題
添加物リスクを語る上で見落とされがちなものに「無機リン」があります。
原材料名には「リン酸塩」「PH調整剤」「乳化剤」「膨張剤」などに含まれる可能性のある化学物質です(※必ずしも含まれるわけではありません)
主にハム・ソーセージ・インスタント製品などに多く含まれ、腎臓に負担をかける可能性があるため、摂取は控えめにするよう奨励されています。
リン自体は身体に必要な必須ミネラルで、「有機リン」といって野菜や魚など、自然な食品にも含まれていますが、化学物質の「無機リン」は吸収率が高く、過剰摂取になりやすいとされています。

添加物が多いと塩分摂取量も増えるため、腎臓にはWパンチ!
できるだけ添加物を減らした食生活を心がけることが健康のためにはよいですね
デリバリーや外食での添加物との向き合い方
デリバリーや外食で添加物について意識するのは、少しハードルが上がります。
アレルギーや特定原材料に関わらない食品添加物は、表示義務がないため、成分が不明なまま摂取することになりがちだからです。
以下のようなおおよその傾向を把握して、「なにをどう食べるか?」を選ぶとよいかもしれません。
たとえば揚げ物は冷めても美味しくするために添加物が使われることがあります。価格の安いデリバリーでは再利用された調理油が多用される傾向があり、健康リスクも懸念されています。
ドレッシングやソースには、保存料や増粘剤などの添加物が多く含まれるため、マイ調味料を別に用意しておくなど、小さな工夫で添加物を意識することが可能です。
原材料名が公開されているサービスや、無添加やオーガニックを売りにした商品を利用するのも有効です。
コラム:食事を見直したら、健康診断の数値が変わった!
添加物は「悪」なのか「善」なのか。その答えはここまでの解説のとおり、はっきり明言できるものではありません。
しかしながら添加物の多い食品は、おしなべて「高カロリー」「高塩分」「高脂質」になる傾向があります。添加物そのものよりも、むしろこちらの方が健康リスクとしての影響が顕著だとは言えます。
実は以前、おーは健康診断で肝機能の値が基準を超えており、「要指導」の状態でした。
そこで食生活を見直し、肝臓への影響が懸念される食品や食習慣を見直し、今では基準値以内に収まっています。
添加物に気を付けたことが直接の要因…とは言えませんが、意識したことで食生活全体の改善につながり、結果的に基準値に戻ったのでは?と自己分析しています。
健康は一日して成らず!
無理なくできる範囲で、少しずつ意識するだけでも、ちょっとした変化があるかもしれませんね。
実践:「無理なく添加物を減らす方法」

ここまでで、なんとなく「添加物を減らしてみようかな」と感じたら、おーが実践している方法を紹介しますのでよかったら試してみてください。
まずは「気になること」を見つける!
すべての添加物を気にするのは大変なので、まずは自分や家族の健康課題について「気になるところ」を探してみましょう。
おーの場合は「肝機能」でしたし、介護家族の「フレイル予防」「高血圧予防」「血栓リスク対策」なども、「気になるところ」です。
すると自分の家族の健康のためには何が必要なんだろう?と、気になり始めます。
「関連の深い添加物は何か」を調べる
「気になるところ」が見つかったら、今度はその「気になるところ」と関連の深い添加物はどんなものがあるのか?を調べます。
「肝臓を疲れさせないようにするには、何に注意すべきかな?」という具合です。具体的な例では、人工甘味料系の添加物、ブドウ糖化糖液糖、アスパルテームやアセスルファムKなどは肝臓での代謝に負担がかかかる可能性が高いと指摘されていたり、赤色102号などの合成着色料は肝機能低下のリスクが懸念されている、などです。
「温度感別」のどのレベルか判断する
どのような添加物があるかを把握できたら、最初に紹介した「温度感別」の比較的安全とされる添加物、注意が必要な添加物、できるだけ避けたい添加物、のどのレベルに該当するかを判断します。
あまり厳格に分けようとしても迷ってしまうので、「なんとなくここ」と割り振ればいいです。あくまで自分の中での基準ですから、あとからレベル変更したくなったらすればいいです。
レベル分けを基準にして「買う/買わない」を決める
食品の「原材料名」に気になる添加物名があったら、レベル分けをリスク許容度の基準として「買おうかな、やめようかな」を決めます。たまにはどうしても食べたいときもありますし、一食食べたからといってすぐに健康状態に影響が出るとは考えにくいですから、あまりルールで縛りすぎないことがストレスなく続けられるコツです。
「買わずに済む方法」を検討する
もし普段買っている商品に気になる添加物が入っていて困ったら、他の商品で添加物不使用のものがないかどうか探してみるのもよいでしょう。案外、同じ売り場なのに添加物の種類の違う商品が並んで売られていたりします。
添加物の入った商品をそもそも使わず、手作りレシピで置き換えができないか検討してみるのもおすすめです。カロリー・塩分・脂質・糖質なども一緒にカットできるので、トータルでの健康効果はぐっと高まります。
ひとつづつクリアする
完璧を求める必要はないので、この方法を気長に続けていくうちに「気になるところ」が改善したきたような兆しが見えればしめたもの!
おーの「肝機能」の例でいえば、次年度の健康診断の結果が目に見えて変化を実感したタイミングです。「添加物」とは少しズレますが、介護状態の母の便通改善など、食事全体の改善につながった実践法も同じ手法を用いています。
「この添加物への注意ができるようになったら、今度は次の添加物にも注意してみよう」「この商品は手作りに置き換えられたから、もう買わなくてもいいや」というように、地道にひとつひとつ繰り返していきました。気づいたら「気になること」が改善していた印象です。
まとめ:「添加物との付き合い方」
今回紹介した添加物に対する考え方や対処の実践方法が正解とは限りません。
食品の選択肢は多様化し、私たちの食生活も変化しています。「中食」や「外食」の需要拡大もあって、添加物入りの食事を口にする機会はこれからも増えていくことでしょう。ります。
添加物のおかげで利便性が向上していることは事実です。どのような食材や加工品を取り入れるかは、それぞれの価値観や健康状態によって異なります。食品添加物について知識を持つことは、自分や家族の健康を守るための大きな力になります。
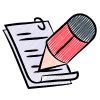 まとめポイント
まとめポイント
・すべての添加物を排除する必要はなく、知って選ぶことが大切。
・「気になるところ」から少しずつ意識して、無理なく取り組んでみる。
・食品を選ぶ目を養えば、外食や中食の際にもより良い選択ができるようになる。