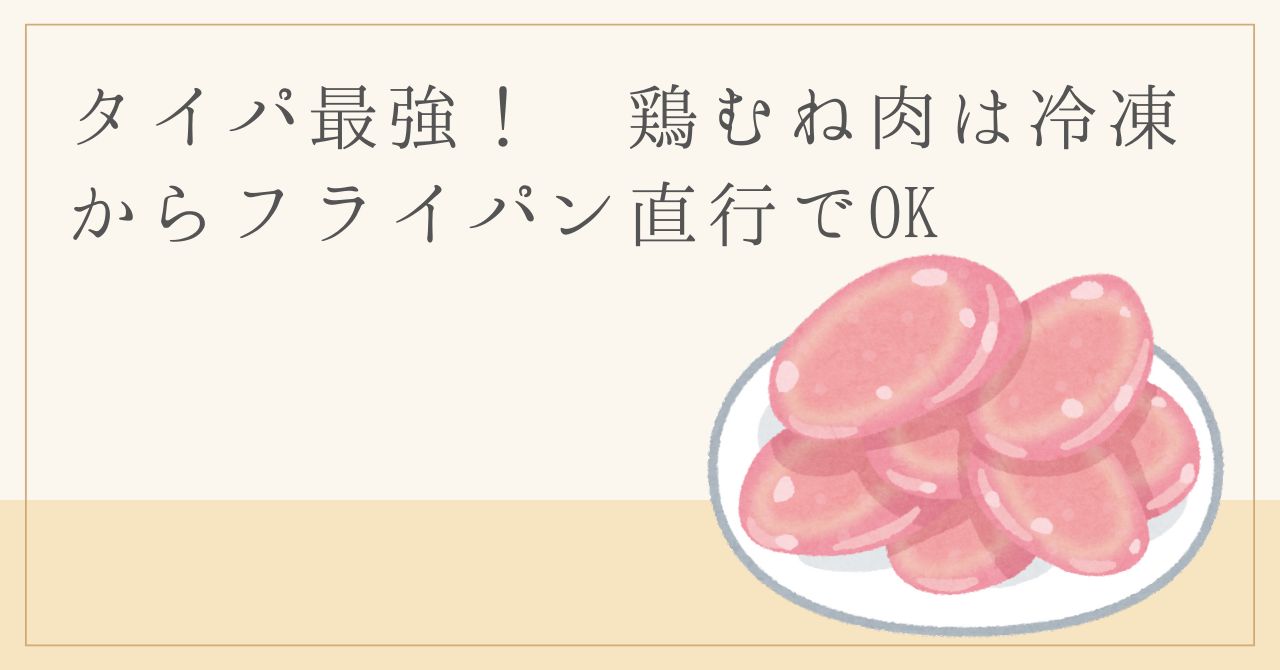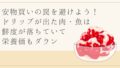「安い」
「脂肪が少なくカロリー控えめ」
「ダイエットや筋トレにもいい」
鶏むね肉は、健康面やコスパの両方で人気の食材です。
でもそれだけではなく、実はこんな隠れたメリットも!
「いろんな肉料理に代用可能」
「冷凍保存が簡単で、解凍なしで調理OK」
「高齢者の栄養補給にも最適」
冷凍のままフライパンにポイ!
加熱後ほったらかしで調理完了!
豚肉で同じことをやったらひっついてしまいますが、鶏むね肉は冷凍・加熱の過程で繊維が緩みやすいので、自然にほぐれてくれます。
冷凍しても食感が損なうこともなく、水分が適度に抜けることで、むしろ柔らかくなり味染みもジューシーに!
特売日に鶏むね肉を買ってストックすれば、食費節約(コスパ)と調理時短(タイパ)のメリットいいとこ取りで、忙しい日の調理時間短縮に効果的ですよ!
この記事では鶏むね肉の栄養管理上のメリット・簡単においしくするコツ・加熱解凍で時短できる便利なレシピなどを紹介していきます!
こんなに凄い!鶏むね肉のメリット5選!
メリット① ダイエットに最適!低脂肪&高たんぱく
100gあたり約110Kcal(皮なし)
皮ありだと約190~200kcalほどと、およそ2倍差。
カロリーを抑えたいな、というときは皮を取った方がよりヘルシーです。
ただし鶏皮にはコラーゲンも豊富なので、捨てるのはちょっともったいない気もしますね。
あえて皮は残したまま、スープや煮込み料理に活用するのもオススメです。スープや煮込み料理なら、コラーゲンが溶け出して、吸収もしやすくなります。
うま味の元にもなるので、取るか残すはお好みで選ぶとよいです!
糖質ゼロ!100gあたり23gの高たんぱく質
たんぱく質含有量は、ささみと並んで最強クラス。
豆腐や卵に比べると、およそ2倍。牛乳と比較すると約7倍もたんぱく質が多く摂取できます。
レシピの応用が多彩で毎日食べても続けやすく、ダイエットにも役立てやすいです!
メリット② 筋トレ・筋力UPに最適!豊富なアミノ酸
アミノ酸バランス満点!筋肉の修復・成長をサポート!
鶏むね肉は、必須アミノ酸のバランスでもトップクラス。
卵やササミ、もも肉などと並んで「アミノ酸スコア100」の満点食材です。
無駄なく吸収され、筋肉の成長を効率よくサポートしてくれます。
脂肪を抑えながら、筋肉量を増やしやすい
低脂肪・低カロリーなので、食べても太りにくいです。
筋肉だけを増やせるので、筋トレやスポーツで体を鍛えたい人には特におすすめ。
また消化もいいので、食が細くてお悩みの方にも向いています。
胃腸への負担が少なく、健康的なボディメイクに役立ちます。
メリット③ 免疫力UP!疲労回復に効果的!
脳、身体の両方に効く抗疲労成分「イミダゾールペプチド」
渡り鳥など、長距離移動でエネルギーを使う鶏肉には「イミダゾールペプチド」という疲労回復物質が多く含まれています。
ニワトリは飛ばない鳥ですが、進化の過程でこの物質を持ち続けています。

空を飛んでいたころの名残でしょうか?(笑
詳しい方がいらしたら教えてほしいです!
この成分には疲労回復や抗酸化作用があり、スポーツ後や疲れが溜まっているときのケアに役立つと期待されています。
脳の疲労回復にも効果があるとされ、集中力維持やストレス軽減にも役立つと期待されています。
豊富なビタミンB6が免疫機能をサポート
鶏むね肉は、ビタミンB6含有量でもトップクラス!
100gあたり0.5mgほどで、これは1日の摂取目安の1/3~1/2をカバーできる量です。
ビタミンB6には、免疫細胞を活性化する働きがあります。
ビタミンB6の1日の推奨摂取量と、鶏むね肉でのカバー率
| 年齢・性別 | 推奨摂取量(mg/日) | 鶏むね肉100gでのカバー率 |
|---|---|---|
| 成人男性 | 1.4mg | 約36% |
| 成人女性 | 1.2mg | 約42% |
| 妊婦 | 1.5mg | 約33% |
👉 鶏むね肉100gで、1日の約1/3~1/2のビタミンB6が補える!
出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
▶ 公式リンク 文部科学省「日本食品標準成分表」
また微量ながら亜鉛も含んでいて、こちらも風邪を引きにくくしたり、コラーゲンの合成をサポートして肌トラブルを解消してくれたりします。
メリット④ 介護の栄養補給・回復食にもマッチ
脂質が少なく、消化に優しい
赤身肉などに比べて鶏肉は、脂身も少ないため胃腸への負担が軽減されます。
肉繊維自体もほつれやすいため、消化吸収もしやすい。鶏むね肉は皮を取りやすいので、胃腸の弱った状態でも比較的食べやすく筋力回復もはやいです。
冷凍すると肉繊維の破壊がされるため、より胃腸に優しくなりますよ。
高齢者の栄養補給におすすめ
鶏むね肉は、大豆と並んで高齢者のたんぱく質補給に最適な食材。
高齢者は、なにもしないと筋肉量が落ちやすいハンデがあります。柔らかく、調理もしやすい鶏むね肉は、たんぱく質不足による筋力低下(サルコペニア)を防ぐのに有効です。

おーの母親は何度も入退院を繰り返していますが、毎回、大豆・鶏ムネ肉レシピを積極的に取り入れて、結果として回復がスムーズになり、寝たきり予防につながっています。
メリット⑤ 長期保存可能なストック食材
まとめ買いして、冷凍庫ストック
鶏むね肉は、冷凍しても食感は大きく変わらず、むしろ味染みがよくなり、美味しく食べることができます。
1か月程度保存可能なので、セール時に買いだめしてストックすれば、食費の節約にもつながります。
ただし見切り品などで割引になっているものは、ドリップ(赤い汁)が発生しているものもあるので注意が必要です。
ドリップについては別の記事で詳しく解説しているので、そちらも参考にしてください。
解凍不要!加熱調理で手間いらず&衛生的
豚肉は凍ったまま加熱すると、肉同士がひっついてしまうため事前に解凍するのが一般的です。
鶏むね肉は、冷凍のまま加熱してもひっつきません。加熱しながら菜箸でほぐす必要もなく、自然にほぐれるのを待てばOK!
低温解凍や自然解凍の時間をカットできるのでとても便利です。
解凍しないことは衛生面でもメリットが大きく、低温から一気に高温になることで雑菌繁殖のリスクが抑えられ、安全に食べることができます。
実践!冷凍庫→フライパン直行の具体的手順
冷凍保存のコツ
冷凍前に、あらかじめ小口切りにしてから冷凍しましょう。袋に詰め替えて、なるべく板状になるよう平らににすると加熱が均一になりやすく、調理しやすくなります。
唐揚げに使うなど用途が決まっていれば、この時点で醤油やショウガで下味をつけて冷凍すると味染みも良くなります。
解凍後に味付けしてもいいので、とりあえずストックしておきたいときは生のまま保存でOKです。
調理は解凍なしでOK!
煮物などは調理途中の適切なタイミングで冷凍庫から出して直接投入しましょう。スープ系や煮物系など「煮汁」がある料理なら、焦げる心配もないのでそのまま放置しても安心です。
炒める場合も直接フライパンにゴトン!と落としてOK!
焦げないよう中火以下で加熱し、自然にほぐれるのを待ちましょう。部分的に加熱されやすいため、外面だけが焦げつかないよう、たまに箸で転がしながらほぐすと失敗しません。
どんな料理にも使いやすい!
クセがなく淡泊なので、和・洋・中どの調味料ともよく馴染みます。
いつものレシピをちょっとアレンジしてみたい…という冒険心が湧いた時も、失敗リスクが少ないので色々チャレンジしてみることをぜひおすすめします!

ベーコンの代わりにミネストローネにしたり、豚肉の代わりに青椒肉絲やチャンプルーなどにも合いますよ。
冬ならお鍋にも合いますし、夏ならササミの代わりに棒棒鶏にしてもボリュームアップして食べ応えがあります。
毎日いろんな料理に入れて楽しみながら栄養管理できるのも、使いやすい鶏むね肉ならではです。
調理器具の洗浄について
鶏肉は細菌が比較的多め
メリット盛りだくさんな鶏むね肉ですが、豚肉や牛肉に比べると付着している細菌(カンピロバクターなどの食中毒菌)が多めです。
鶏肉独特の「ぬめり」を気にして水道水で洗うと、水しぶきに細菌が付着して辺り一面に飛散するので絶対にNGです!
肉に直接触れた手で目や口を触るのも絶対に避けましょう。
殺菌消毒の重要性
精肉の調理につきものなのが、面倒な調理器具の後始末です。
包丁やまな板は、衛生上しっかり洗わなければいけませんが、どのような点を注意すればよいでしょうか?
農林水産省では、85℃以上の熱湯で1分以上の消毒を奨励しています。食用洗剤で洗浄を基本とし、塩素系漂白剤での消毒も奨励。包丁やまな板は生肉・魚介用の専用のものを用意することが望ましいとし、洗浄後のスポンジやたわしについても、十分な乾燥と、こまめな交換を推奨しています。
とはいえ徹底はなかなか大変

正直ここまでやるのはけっこう大変です
・魚肉専用に使い捨てまな板シートを使う
・抗菌手袋を着用して調理する
・あらかじめカット済みの商品を購入する
などの工夫で作業負担と食中毒リスクをなるべく減らすのがよいでしょう。
まとめ
鶏むね肉の魅力について解説してきましたが、どうでしたか?
長くなったので、まとめます。
1. 記事の振り返り(ポイントの再確認)
👉 鶏むね肉のメリット
👉 冷凍保存・調理のコツ
👉 衛生管理のポイント
2. 実践しやすいポイント(この記事で伝えたいこと)
👉 「まとめ買い&冷凍ストックで節約&時短!」
👉 「冷凍のまま調理OK!手軽にヘルシーメニュー」
👉 「まな板・包丁の衛生管理は正しい工夫で」
参考になれば幸いです。